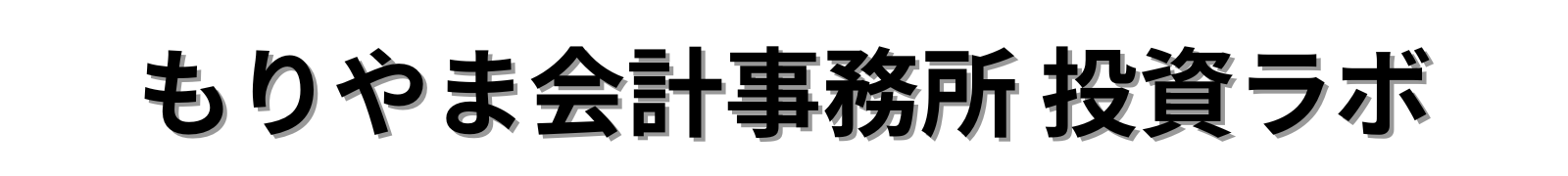譲渡制限付株式報酬とは譲渡制限付株式による報酬のことです。この記事では主に譲渡制限付株式報酬について解説します。
譲渡制限付株式報酬とは
譲渡制限付株式報酬とは契約等により譲渡制限が付された株式(譲渡制限付株式)による報酬のことです。報酬として発行される譲渡制限付株式は「リストリクテッド・ストック」やその頭文字の「RS」と言われることもあります。
2016年度の法人税法改正により一定の譲渡制限付株式報酬の損金算入が認められることとなったことを機に、上場会社では譲渡制限付株式が役員・従業員に対するインセンティブ報酬として活発に発行されるようになってきました。
譲渡制限株式とは
「譲渡制限付株式」と混同しやすいものが「譲渡制限株式」です。譲渡制限株式とは、「株式会社が発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における株式」のことです。非公開会社が発行している株式が譲渡制限株式です。
譲渡制限付株式は契約により譲渡制限が付されているのに対して、譲渡制限株式は会社法により譲渡制限があるところが根本的な違いです。
譲渡制限付株式報酬の仕組み
譲渡制限付株式のインセンティブ報酬としての仕組みについて時系列で解説します。
①会社が役員・従業員に役務提供の対価として債権を支給する
譲渡制限付株式をインセンティブ報酬として利用するものであるため、ここでの役務提供とは職務・労働の提供のこと、債権とは報酬に対する債権のことです。
②役員・従業員が債権を現物出資する
役員・従業員が報酬債権を現物出資します。現物出資の価額は株価に株式数を掛けたものとされることが一般的です。
③会社が株式を交付する
株式の交付は新株式の発行や自己株式の処分の方法により行われます。この株式は役員・従業員との契約により「本払込期日から〇年〇月〇日までの間、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない」などの譲渡制限が付けられます。なお、譲渡制限付株式は証券会社の専用の口座で管理されているため譲渡制限には実効性があります。
④役員・従業員が会社に役務提供する
先述の通り役務提供とは職務・労働の提供のことです。
⑤譲渡制限が解除される
譲渡制限付株式の譲渡制限が解除されると役員・従業員は株式を処分することができます。そのまま保有することも売却することもできます。譲渡制限が解除されることで実質的に役務提供の対価として株式が交付されたことになります。
譲渡制限付株式報酬の会計処理
譲渡制限付株式の会計処理を設例で解説します。
(例)当社(3月決算)はX1年4月1日に当社取締役3名にインセンティブ報酬として譲渡制限付株式を発行した。譲渡制限期間は払込期日から3年であり、譲渡制限の解除条件は譲渡制限期間中継続して取締役の地位にあることである。その他、発行の概要は以下の通りである。
払込期日:X1年4月1日
株式の数:300株
発行価格:1株につき10,000円
発行総額:3,000,0000円
(解説)
払込期日(X1年4月1日)
払込期日には現物出資された債権を前払費用として計上します。前払費用として計上する理由はまだ提供されていない役務の対価だからです。また、新株を発行して全額資本金とする場合は出資された額を資本金で計上します。
| 払込期日(X1年4月1日) | |||
| 前払費用 | 3,000,000(※1) | 資本金 | 3,000,000 |
(※1)発行価格10,000円×株式の数300株
決算時
決算時には役務提供の期間に応じて前払費用を株式報酬費用に振り替えます。株式報酬費用は株式等で支払われた人件費を示す勘定科目であり、販管費に計上されます。
| 決算時(X2年3月31日) | |||
| 株式報酬費用 | 1,000,000(※2) | 前払費用 | 1,000,000 |
| 決算時(X3年3月31日) | |||
| 株式報酬費用 | 1,000,000 | 前払費用 | 1,000,000 |
| 決算時(X4年3月31日) | |||
| 株式報酬費用 | 1,000,000 | 前払費用 | 1,000,000 |
(※2)発行総額3,000,000円×12か月÷36か月
譲渡制限付株式報酬損益計算書への影響
譲渡制限付株式が発行されると期間に応じて損益計算書に株式報酬費用が計上されます。
株式報酬費用の特徴はキャッシュ・アウトがない費用ということです。実際にはキャッシュ・アウトがないにもかかわらず費用が計上される理由は、会社に提供された役務(職務・労働の提供の事実)を損益計算書に反映するためです。
譲渡制限付株式報酬のメリット
役員・従業員に対する報酬を金銭の支給ではなく譲渡制限付株式の発行で行うことにはメリットがあります。
譲渡制限付株式報酬は報酬が株式であるため株主との価値共有をすることができ、譲渡制限が付されていることにより企業価値の持続的な向上を図ることができます。これにより譲渡制限付株式の発行は役員や従業員にとっても、株主にとってもメリットがあると考えられています。
譲渡制限付株式報酬のデメリット
譲渡制限付株式の発行にはデメリットもあります。
先述のとおり譲渡制限付株式報酬は損益計算書に費用が計上されます。また、株式の発行や自己株式の処分による希薄化が起きます。あくまで報酬であり大規模な新株発行や自己株式の処分が行われることが少ないため、一般的に強調されることはありませんが、このようなデメリットがあるのも事実です。
譲渡制限付株式報酬により役員・従業員と株主の利害関係が一致
役員(取締役)と株主はエージェンシー関係にあり利害関係が対立しています。しかし、譲渡制限付株式をインセンティブ報酬として発行することにより、企業価値、つまり、株価の上昇が役員・従業員の報酬額に直結するため、役員・従業員と株主の利害関係が一致します。
譲渡制限付株式の発行により短期的には費用の計上・希薄化によりEPSの低下要因になりますが、長期的には役員と株主の利害関係の一致により今後の業績に期待できる可能性があります。