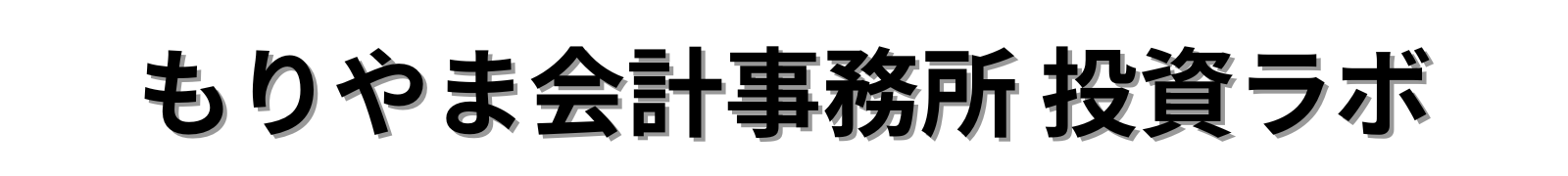今回は投資と関係の深い財務諸表監査についての話です。投資に関する読み物として気軽に読んで頂ければと思います。
監査とは
デジタル大辞泉によると「監査」という言葉は監督・検査という一般的な意味を持つ一方、会計監査・業務監査という特定のサービスを意味することがあります。
投資の世界で監査というと後者の会計監査の意味合いが強く、今日はこの会計監査、つまり、財務諸表監査についてご紹介します。
1 監督し検査すること。
2 特に会計監査・業務監査のこと。
「監査」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書
財務諸表監査の必要性
財務諸表監査はなぜ必要なのでしょうか。
上場企業は銀行や株主から資金調達することにより事業を行っていますが、銀行や株主は融資・投資の判断をする上で会社の業績を決算書で確かめます。
この決算書は会社が自ら作成したものであり、それが本当に正しいかは銀行や株主には分かりません。
そこで、決算書を、第三者である監査法人(会計監査の専門家である公認会計士が所属する会社)が財務諸表監査をすることにより、決算書を一定水準で保証しています。
この仕組みにより私たち投資家は安心して株式の取引ができることになります。有価証券報告書などの決算書を全く見ない投資家も多くいますが、四季報を見たり投資関連のニュースを無条件に信頼できるのは決算書が正しいという前提があるからです。
財務諸表監査はどのように行う?
個人投資家は監査の現場を知らないため財務諸表監査がどのように行われているか気になるところでしょう。
監査は決算書の金額が正しいかを確かめるために、会社担当者への質問、取引先や銀行への質問、証拠書類との照合、公認会計士による数値の分析などにより行われます。
例えば、「売上」であれば販売時の契約書や出荷伝票、納品書などと照合したり、「仕入」であれば仕入先からの請求書などと照合したりすることにより「売上」や「仕入」の発生の事実や計上漏れがないことを確かめます。
また、「預金」や「借入金」であれば銀行へ確認書を送付してその回答から「預金」が実在していることや「借入金」の計上漏れがないことなどを確かめます。
他には「支払利息」であれば借入金の残高と利率から理論的な利息の額を算出して比較分析することなどが行われます。
会計不正はなぜ起こるか
監査があるのになぜ会計不正が起こるのでしょうか。
実は監査では会社の取引の全部ではなく一部についてのみサンプルでチェックをしています。その理由は、全ての取引をチェックすることはコストや人員・時間の関係から事実上不可能であり(今のIT環境では監査に天文学的な費用がかかることになります)、一部についてのみサンプルでチェックすることで統計学上十分な信頼が得られるためです。
そのため、監査は絶対的な保証ではなく、一定水準の保証となるのです。
私が会計士の受験生時代にある予備校の監査論の講師が監査についてこう例えていました。
「監査は味噌汁の味見と同じ。味見をするために鍋の味噌汁を全部飲む奴はいない」
これは非常に分かりやすい例えだと思います。
よく会計不正が起こるとテレビ番組で評論家などが「監査法人は何をしてたんだ」と言うことがあります。確かに監査法人の人員・時間などのリソース不足による品質低下の影響も否定できないと感じることもありますが、監査が一定水準の保証であることは一般的には理解されていないようです。
投資家としての心構え
先述の通り、監査は絶対的な保証ではなく一定水準の保証です。だから言って、投資家が適正な意見が出ている決算書について「この決算書は正しいのか?」と考えることはナンセンスです。無限定適正意見が表明されている限り、一度は正しいもとのして財務諸表を見ない限り、何の判断できなくなってしまうからです。
投資家としては監査は絶対的な保証ではなく一定水準の保証であるということを頭の片隅に置いておけば十分でしょう。