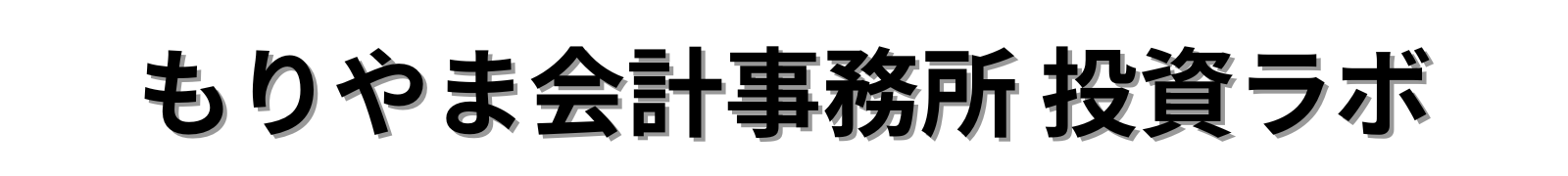小規模企業共済とは小規模企業のための退職金制度です。この記事では小規模企業共済について解説します。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、小規模な会社の経営者や個人事業主のための退職金制度です。毎月掛金を積み立てて、廃業・退任時等に共済金を受け取り、退職後の生活資金として利用することができます。節税効果の高さや退職金代わりにできることから、多くの経営者や個人事業主が共済に加入しています。
小規模企業共済のメリット
高い節税効果
小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額を所得から控除することができるため高い節税効果があります。また、将来受け取る共済金は、65歳未満で任意解約する場合や掛金未払で強制解約となる場合を除き、「退職所得」または「公的年金等の雑所得」となり、税制上優遇されています。
退職金代わり
小規模な会社の経営者や個人事業主は退職金を準備するのが困難なため小規模企業共済を退職金代わりにできます。小規模企業共済を運営する独立行政法人中小企業基盤整備機構はいわゆる「機関投資家」であり、共済の掛金は株式や債券などで運用されています。
小規模企業共済の節税効果
小規模企業共済には高い節税効果があります。節税額は「掛金の額×税率」で計算できます。下記は具体的にどれぐらいの節税ができるかについて、所得と年間の掛金の額でパターン分けして表にしたものです。
| 所得/掛金の額 | 120,000円 | 240,000円 | 360,000円 | 600,000円 | 840,000円 |
| 600万円 | 36,500円 | 73,000円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,500円 |
| 800万円 | 40,100円 | 80,300円 | 120,500円 | 200,800円 | 281,200円 |
| 1,000万円 | 52,400円 | 104,800円 | 157,200円 | 262,100円 | 367,000円 |
例えば、納税者の所得が600万円、年間の掛金の額が120,000円の場合、節税額は120,000円×30.42%=36,500円です。税率は復興特別所得税率2.1%を考慮した所得税の速算表の税率に住民税率10%を足したものです。
なお、設定できる掛金の額は年間で最低12,000円(月額1,000円×12か月)、最高840,000円(月額70,000円×12か月)です。掛金の額に関わらず節税効果がありますが、掛金が少なすぎると節税を実感しにくいでしょう。
確実性の高い投資!?
経済的には支出を減らすことと収入を増やすことは同義です。
先ほどの例では納税者の所得が600万円、年間の掛金の額が120,000円の場合、節税額は36,500円でした。これは120,000円の投資で36,500円の利益があったことと経済的には全く同じです。単年度の利益率は税引き後で30.41%です。
ただし、単年度の利益であることには注意が必要です。実際に共済金を受け取るまでには長い期間あるため、その間の機会損失が心配な場合は、掛金を年々増やして後加重にするという戦略が考えられます。
資産形成のポートフォリオ
資産形成はリスク分散の観点から株式だけ・FXだけ・暗号資産だけなどのように偏らないようにする必要があります。小規模企業共済の掛金は機関投資家である機構が安全な債券を中心に運用しているため、資産形成のポートフォリオの1つとして考えることもできるでしょう。